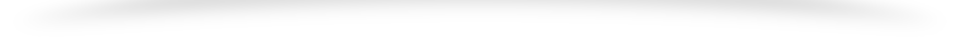「体に良い」だとか「健康に役立つ」という名目で食について語る人は多く、また心と身体の健やかさに寄与するような食べ物は溢れています。
それらについての知識を増やせば増やすほど、食事があらかじめ仕入れた知識や、想定との照らし合せにすぎなくなっているのではないでしょうか。
私たちは食べ物ではなく「情報」を食べているといっていいかもしれません。
「何をどれだけ食べればいいのか」は本来は食欲が導き出すものですから、自らの身体に問うてみて初めてわかることです。
その上、「お昼になったから食べよう」といった具合に、食べたいのかどうかもわからないまま、せっせと食べ物を口に運ぶ習慣を身につけてしまっています。
そのようなことに思い至るようになったのは、禁糖を終えた後、ふたたび菓子を口にするようになってからです。とりわけコンビニに陳列されている商品を見るにつけ、いまの時代における食事の意義を考えるようになりました。
いつの頃からか小さな袋に入ったスナックやちょこっとつまめるくらいの菓子を多く見かけるようになりました。主にオフィスで働く人に向けた商品なのでしょう。
ここでいう「小腹が空いた」という感覚は食欲に由来していると思いがちですが、その正体は「口寂しさ」だと思います。
自分の中に空いた隙間を埋めようとして食べたところで、満腹になりはしても満足は得られないでしょう。食べることで得られる刺激に寂しさの肩代わりをさせれば、いっときの快楽になりはします。
埋めようのない心の隙間を私たちは寂しく感じています。ぽっかり空いているから「手持ち無沙汰」に感じもし、不安になりもする。これらは飢餓感であって決して飢えではないのです。
本格的ではなくとも、「ファスティング」で半日から数日程度の断食を試みることも珍しくはなくなっているくらいには、「食べない」という選択に関心を寄せる人が増えています。
私の場合、断食によって特別な何かを得たということはありません。
ただ日常の自分のありようが見えてきました。飢餓を自らに呼び込むことで、飢餓感の「感」が示すところの不安や寂しさがあぶり出されたからです。
いつも他人に評価されることを望みながら、そうはなれない自分に対して憤懣を感じていました。評価にかなうよう努力をしても、そもそもそれが自分のやりたいことではない。
けれども食を断つことによって、普段は見ないようにしている心の奥がうかがえ、直面したくない自分が浮上して来るのは間違いないと思います。
他者によって自分がジャッジされることに慣れ過ぎて、私たちは自らを観るのを怠っています。断食とは、観念的なアイデンティティーの探索ではなく、身体によって自らと向き合う時間といえます。
断食をすれば「すっきりする」「デトックスできる」と成果や成長を最初から求めても、その通りの答えは得られないでしょう。
私たちは日々自分を装う術には巧みになっていても、素顔をさらすことは恐れています。そういう意味では断食とは、自らを開示するという滅多にできない体験をもたらしてくれるのではないかと思います。
文:尹雄大